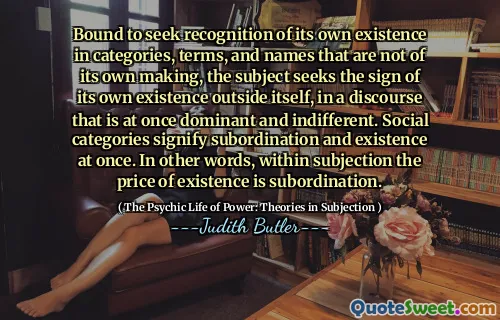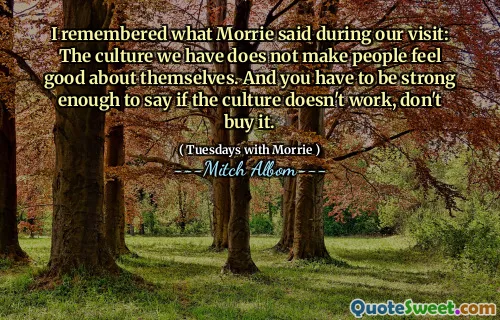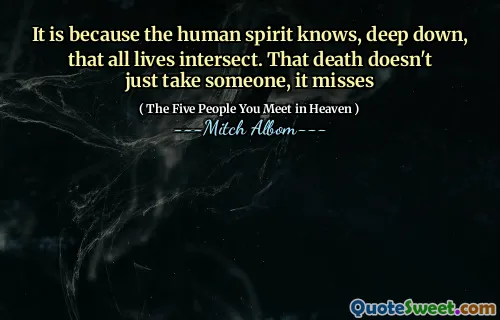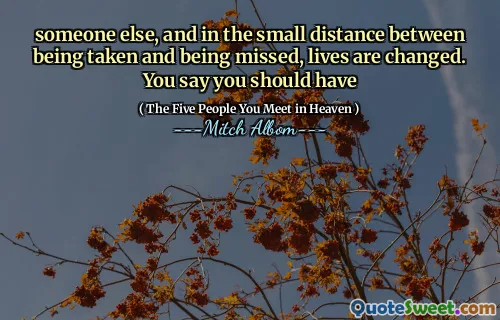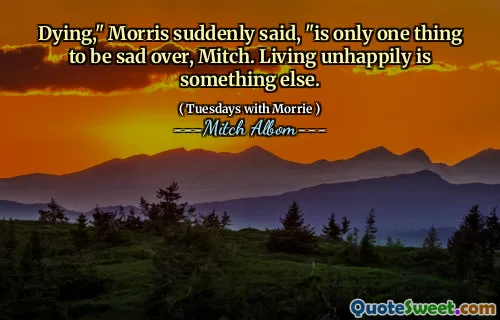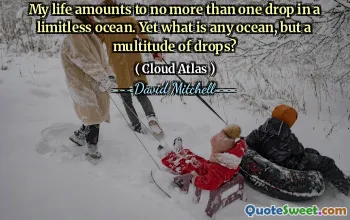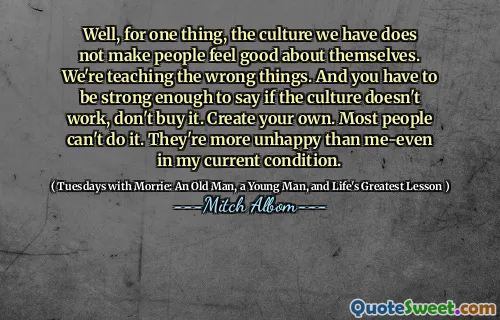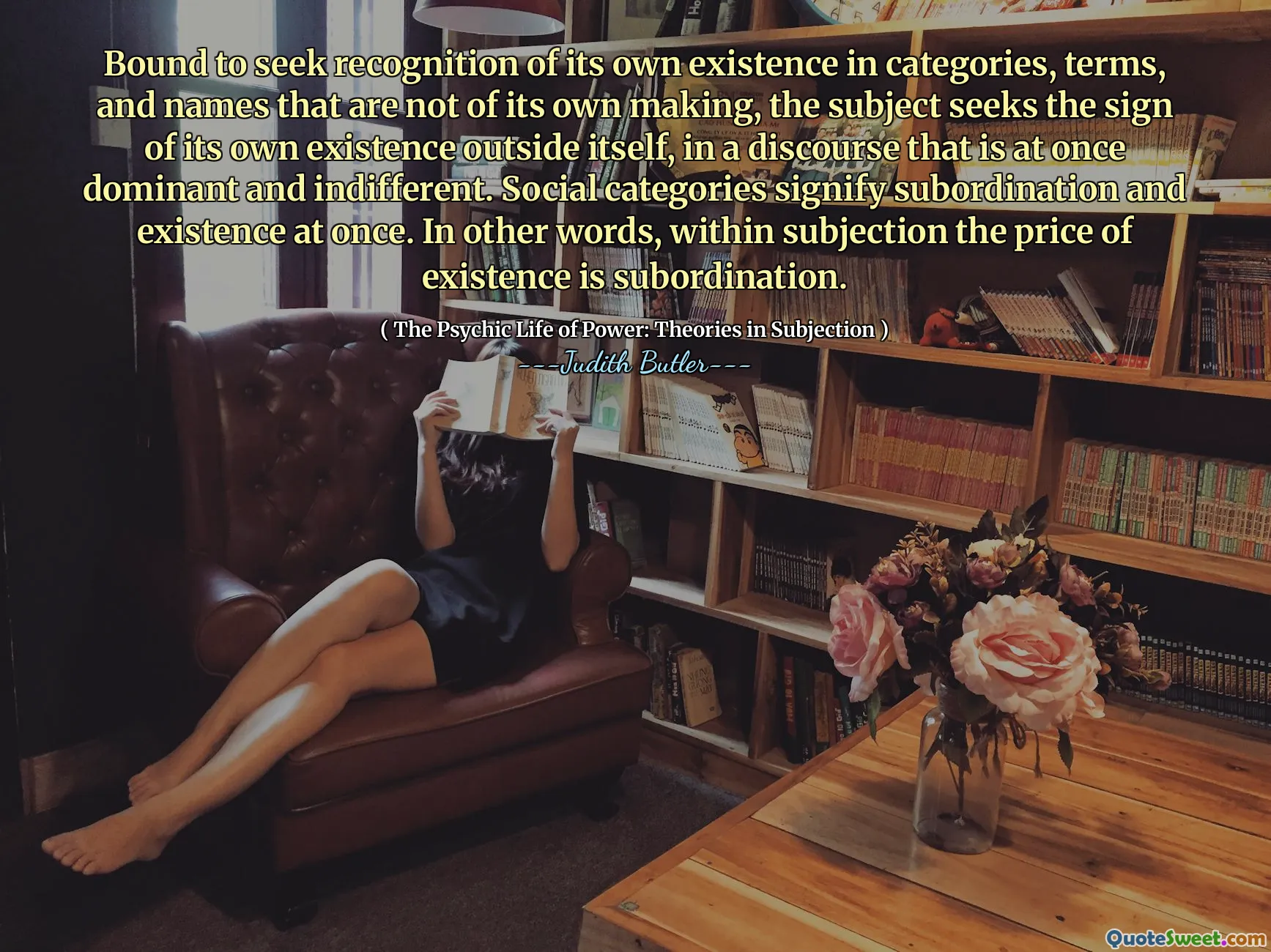
主題は、それ自体が作っていないカテゴリー、用語、名前における自分自身の存在の認識を求めることに縛られており、その主題は、それ自体の外で、それ自体が一度に支配的で無関心な談話で、それ自体の存在の兆候を求めています。社会的カテゴリーは、一度に従属と存在を意味します。言い換えれば、服従内で存在の価格は従属です。
(Bound to seek recognition of its own existence in categories, terms, and names that are not of its own making, the subject seeks the sign of its own existence outside itself, in a discourse that is at once dominant and indifferent. Social categories signify subordination and existence at once. In other words, within subjection the price of existence is subordination.)
ジュディス・バトラーの「権力の精神生活」で、著者はアイデンティティと社会的認識の複雑な関係を探ります。個人または主題は、社会によって作成されたフレームワークと用語の中で承認を求めて努力します。この追求は、自分の存在に対する社会的検証への依存を明らかにし、個人が内部検証ではなく外部の兆候を通して自分自身を肯定しようとする方法を示しています。
バトラーは、社会的カテゴリーはしばしば、従属が存在に固有の階層を反映していることを強調しています。個人のアイデンティティは、これらの構造内の位置によって形作られ、認識の必要性は征服のコストに伴います。したがって、社会内に存在するためには、下位の役割を受け入れることを強いられ、制限と階層を同時に実施するフレームワークでアイデンティティを求めて努力するパラドックスを強調することができます。