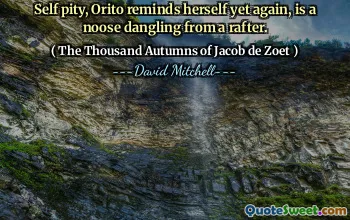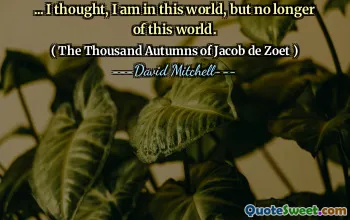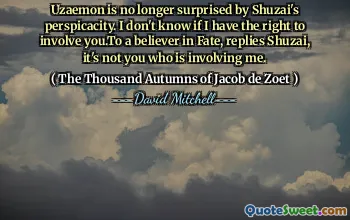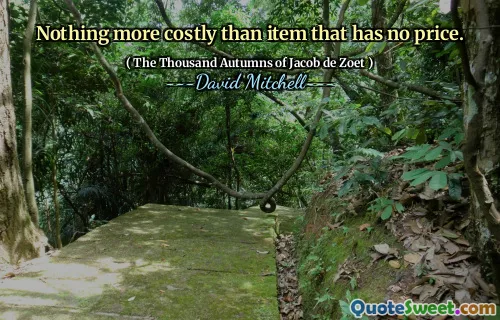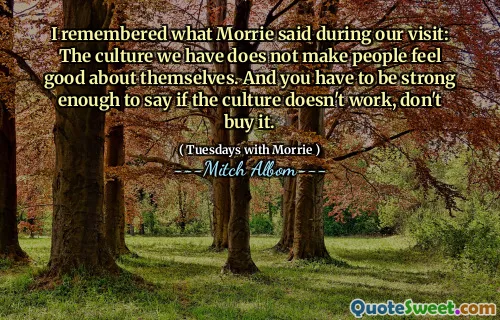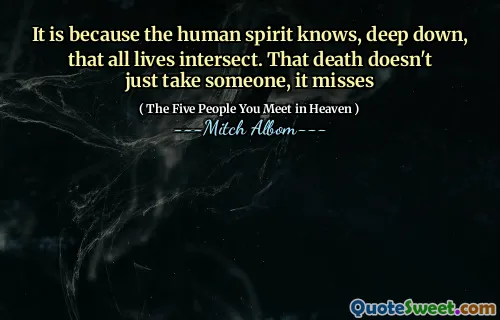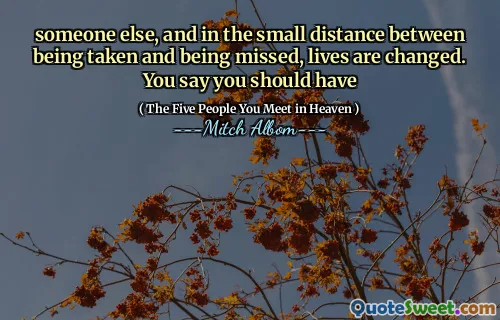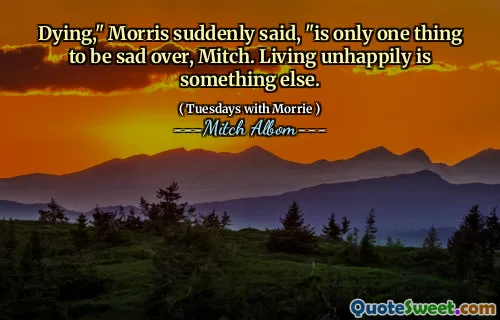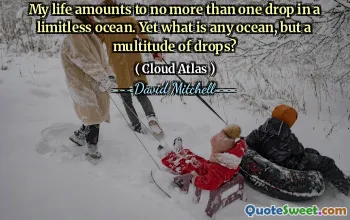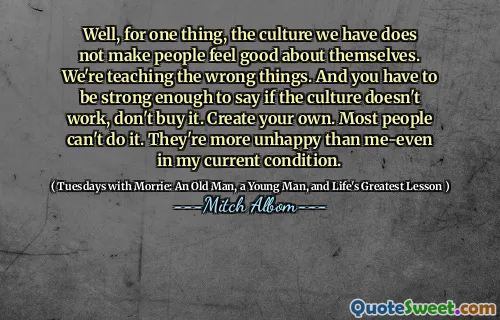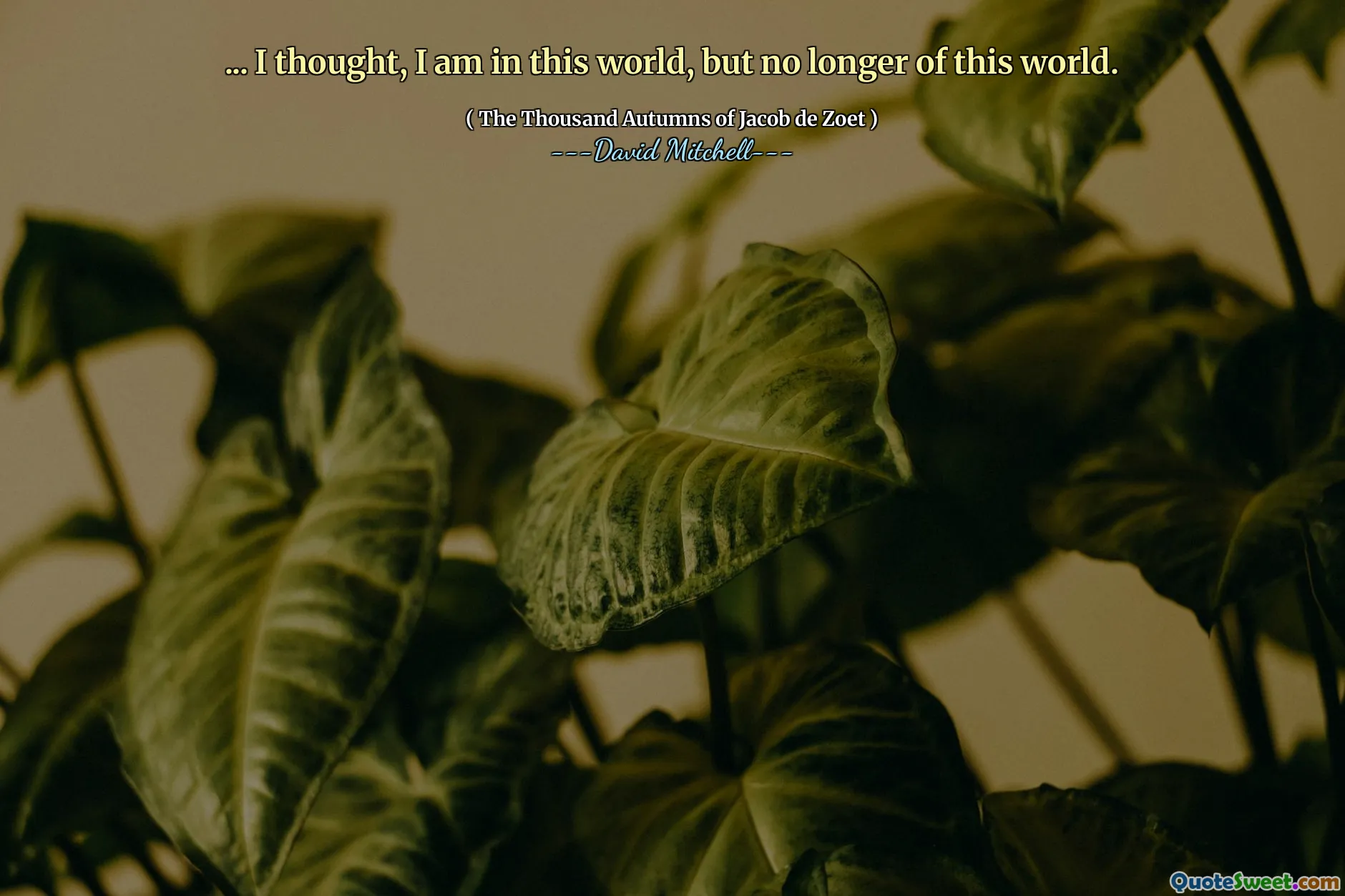
...私はこの世界にいますが、もうこの世のものではない、と思いました。
(... I thought, I am in this world, but no longer of this world.)
(0
レビュー)
『ジェイコブ・デ・ゾートの千の秋』では、著者のデヴィッド・ミッチェルは、世界における自分の立場についての登場人物の考察を通して、帰属と無執着のテーマを探求しています。 「私はこの世界にいると思ったが、もうこの世のものではない」という引用は、個人が物理的に存在しているにもかかわらず、周囲や社会から精神的に距離を置いていると感じる、実存的な分離の感覚を要約しています。
世界の一部であると同時に疎外感を感じているというこの概念は、物語全体に深く響き渡ります。この作品は、外部の課題の中で自分のアイデンティティと格闘するという内部の葛藤に焦点を当て、たとえ慣れ親しんだ環境であっても、個人的な経験がどのように深い孤立感につながる可能性があるかを示しています。
Rate the Quote
コメントとレビューを追加
ユーザーレビュー
0 件のレビューに基づいています
レビューはまだ追加されていません。
コメントがスパム,虐待的,トピック外,冒とく的,個人攻撃的,またはあらゆる種類の憎悪を助長する場合,コメントは投稿が承認されません。
もっと見る »
Today Birthdays
1970 -
Shonda Rhimes
1599 -
Edmund Spenser
1940 -
Edmund White
1957 -
Lorrie Moore
1691 -
George Fox
1961 -
Wayne Coyne
1934 -
Carolyn See
1965 -
Bill Bailey
1967 -
Masha Gessen
1937 -
George Reisman
1890 -
Elmer Davis
1978 -
Nate Silver
1884 -
Sophie Tucker
1960 -
Matthew Bourne
1980 -
Maria de Villota
1977 -
Orlando Bloom
1976 -
Michael Pena
1952 -
Geoffrey Canada
1951 -
Frank Peretti
1955 -
Trevor Rabin
1808 -
Salmon P. Chase
1947 -
Robert Martin
1927 -
Sydney Brenner
1926 -
Carolyn Gold Heilbrun
1954 -
Denise Morrison
1960 -
Eric Betzig
1968 -
Traci Bingham
1919 -
Robert Stack
1970 -
Keith Coogan
1989 -
Beau Mirchoff
もっと見る »