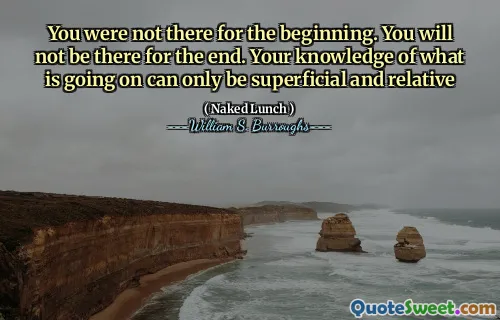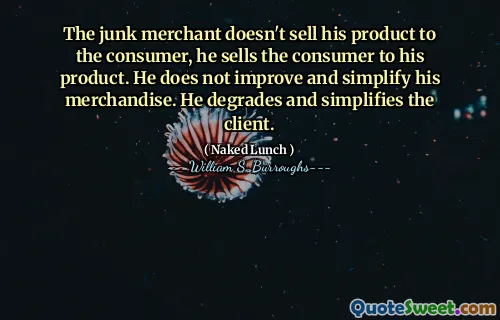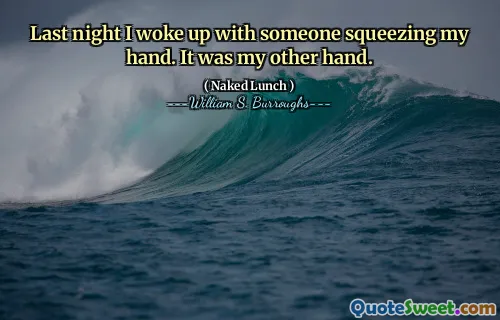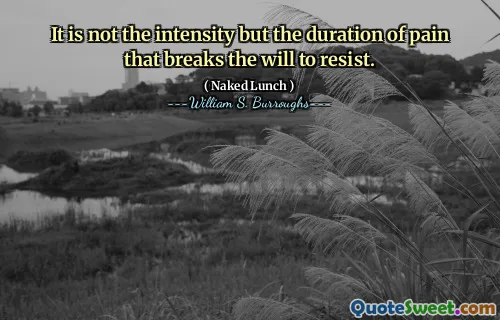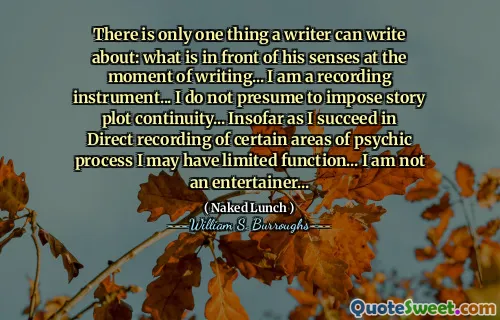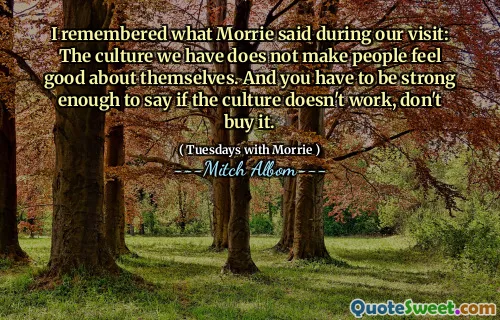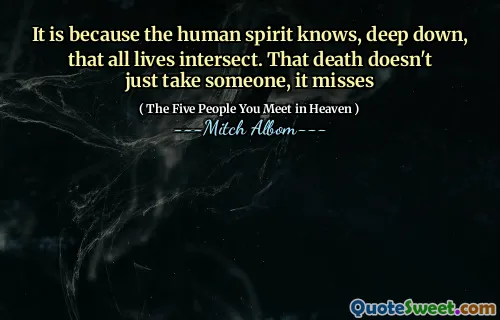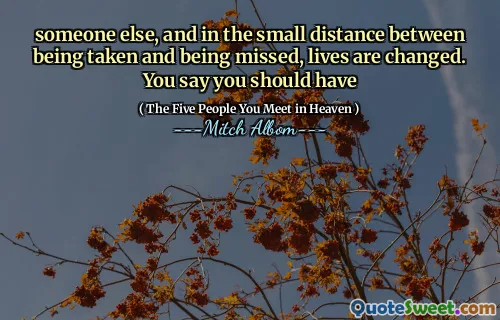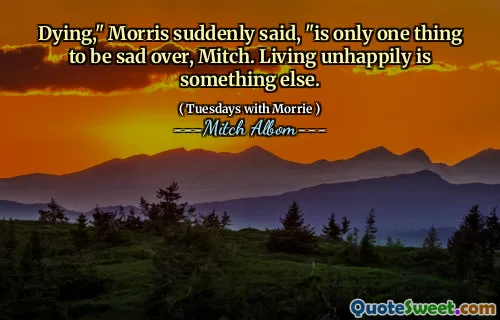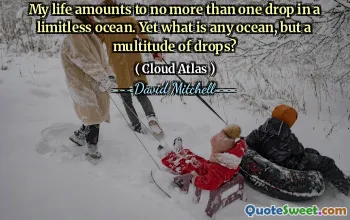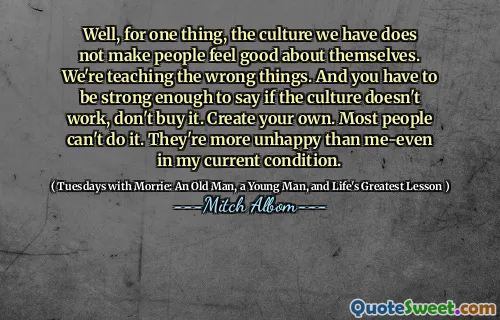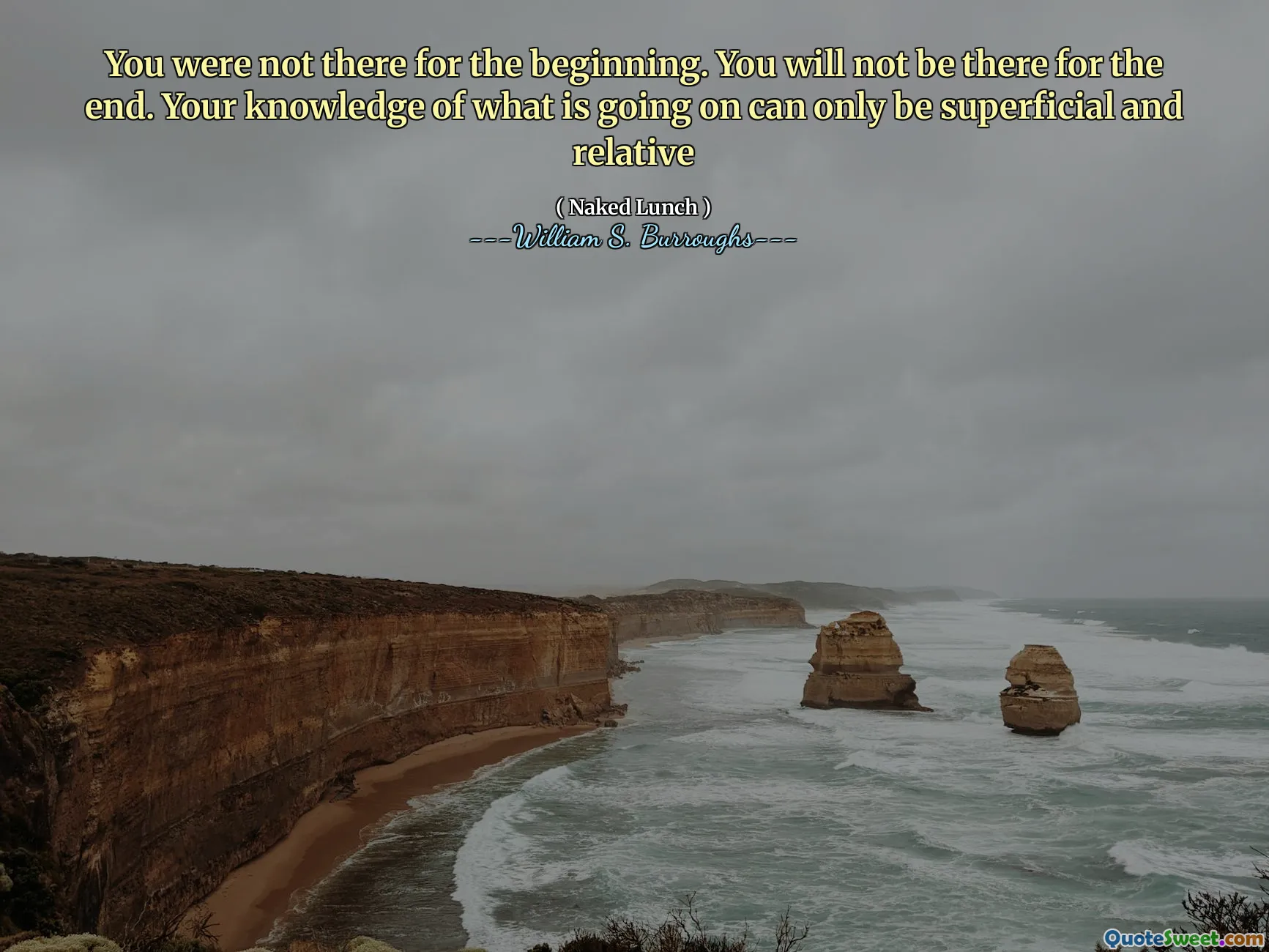
あなたは最初はそこにいませんでした。あなたは終わりにそこにいないでしょう。何が起こっているのかについてのあなたの知識は、表面的で相対的なものにしかできません
(You were not there for the beginning. You will not be there for the end. Your knowledge of what is going on can only be superficial and relative)
(0
レビュー)
「裸の昼食」では、ウィリアム・S・バロウズは存在の基本的な側面から排除された感覚を伝えています。引用は、人生と出来事の理解は、始まりを目撃しなかったか、終わりを経験しないため、限られていることを強調しています。これは、人間の経験の一時的な性質と現実の全体像を把握できないことを認識する哲学的視点を示しています。
バロウズは、知識は本質的に部分的かつ主観的であり、絶対的な真実ではなく個々の経験によって形作られていることを示唆しています。この視点は、読者が知覚の制約性を反映し、私たちが知っていると思うことの多くは、人生の連続体の包括的な理解ではなく孤立した瞬間に基づいているという考えを強化するように誘います。
Rate the Quote
コメントとレビューを追加
ユーザーレビュー
0 件のレビューに基づいています
レビューはまだ追加されていません。
コメントがスパム,虐待的,トピック外,冒とく的,個人攻撃的,またはあらゆる種類の憎悪を助長する場合,コメントは投稿が承認されません。
もっと見る »
Today Birthdays
1729 -
Edmund Burke
1949 -
Haruki Murakami
1954 -
Howard Stern
1876 -
Jack London
1993 -
Zayn Malik
1951 -
Kirstie Alley
1863 -
Swami Vivekananda
1923 -
Alice Miller
1987 -
Naya Rivera
1825 -
Brooke Foss Westcott
1944 -
Joe Frazier
1951 -
Rush Limbaugh
1964 -
Jeff Bezos
1978 -
Jeremy Camp
1628 -
Charles Perrault
1856 -
John Singer Sargent
1970 -
Kaja Foglio
1953 -
Rick Santelli
1986 -
Gemma Arterton
1968 -
Raf Simons
1958 -
Christiane Amanpour
1966 -
Olivier Martinez
1996 -
Ella Henderson
1917 -
Maharishi Mahesh Yogi
1949 -
Ottmar Hitzfeld
1928 -
Ruth Brown
1968 -
Heather Mills
1946 -
George Duke
1968 -
Rachael Harris
1923 -
Ira Hayes
もっと見る »