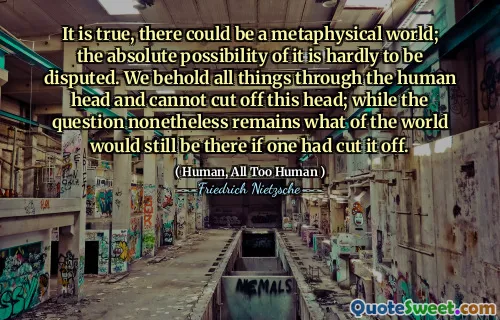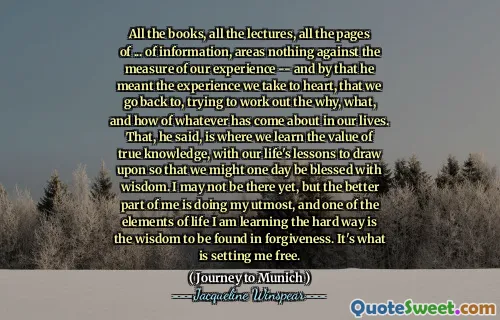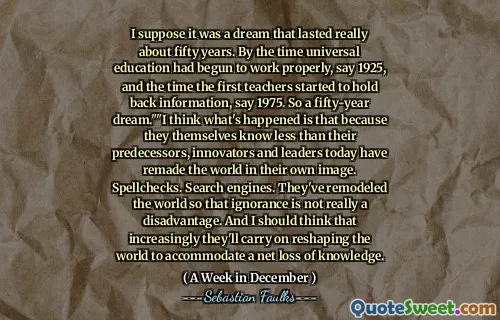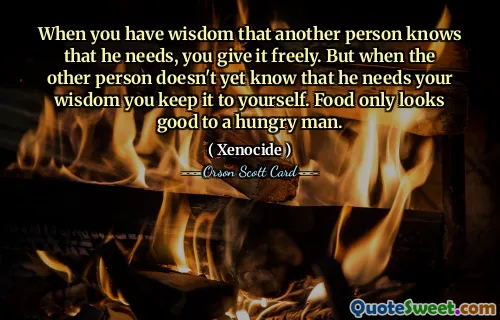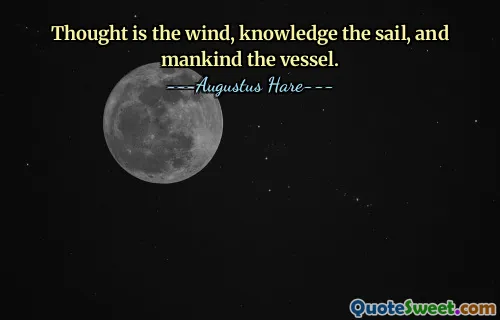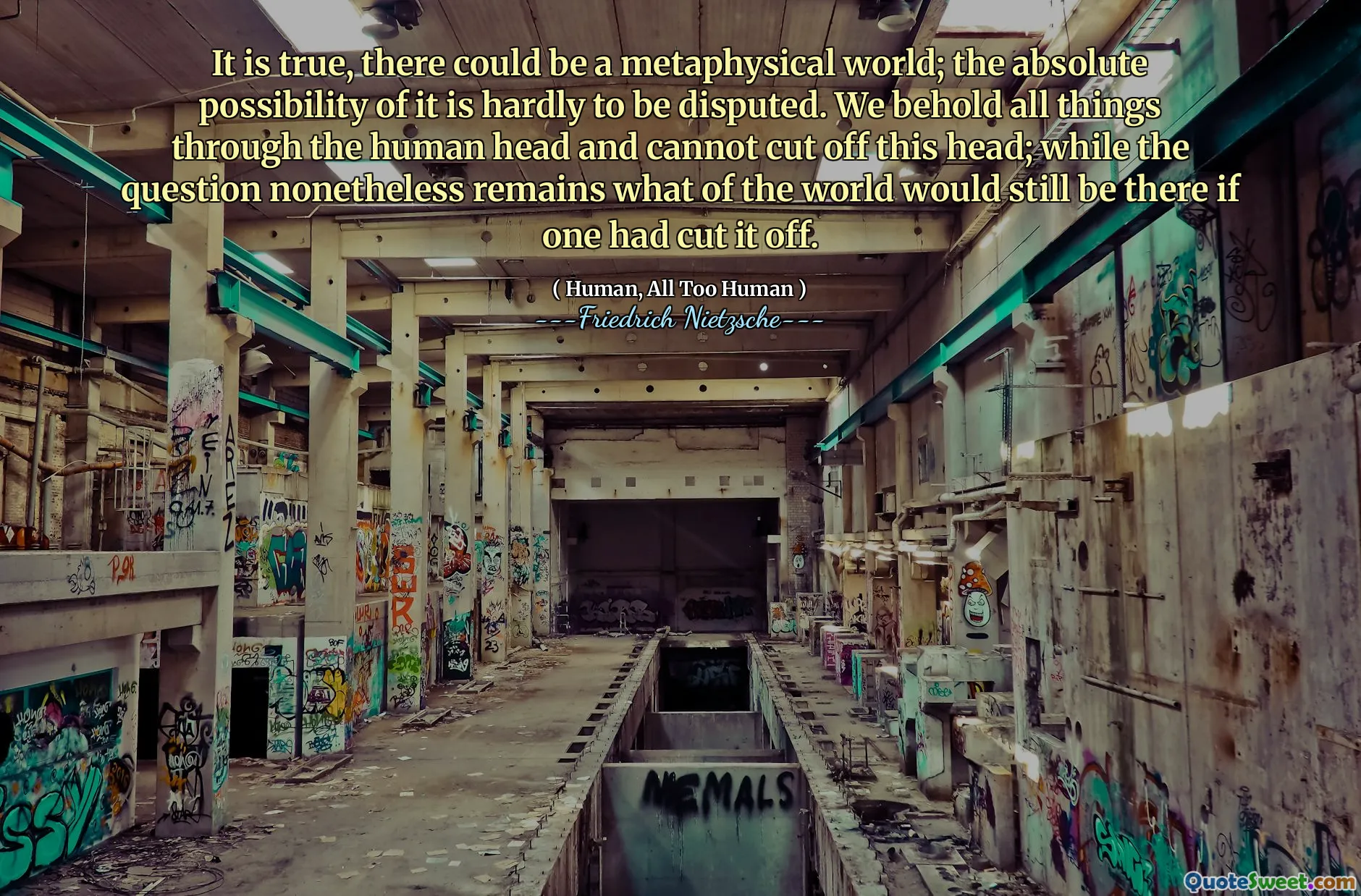
確かに、形而上学的な世界が存在する可能性はあります。その絶対的な可能性には異論の余地はほとんどありません。私たちは人間の頭を通してすべてのものを見ますが、この頭を切り取ることはできません。しかし、もしそれを切り取ったとしたら、世界には何が残るだろうかという疑問は依然として残ります。
(It is true, there could be a metaphysical world; the absolute possibility of it is hardly to be disputed. We behold all things through the human head and cannot cut off this head; while the question nonetheless remains what of the world would still be there if one had cut it off.)
フリードリヒ・ニーチェのこの引用は、現実と人間の認識の性質についての深い哲学的探求を要約しています。ニーチェは、形而上学的世界、つまり物理的現実を超えた無形の領域の潜在的な存在を示唆しています。彼は、その絶対的な可能性は簡単に否定できないことを認めています。しかし、批判的な注目を集めているのは、彼が強調している認識論的制約です。人間は、すべてのものを自分自身の認知能力、つまり「人間の頭」を通して濾過して認識しているのです。この比喩は、人間の認識が現実から切り離せないことを強調しており、すべての経験は必然的に主観的であり、人間の意識の枠組みの中で解釈されることを意味します。
ニーチェが提案した思考実験――「首」が切り落とされた場合に世界には何が残るのかを考える――は、存在論(あるがまま)と認識論(あるがままをどのようにして知ることができるのか)との間の抗しがたい緊張関係を掘り下げている。それは、私たちの理解のどれだけが観察者に依存しているのか、そしてどれだけが独立して存在しているのかという疑問を私たちに投げかけます。この洞察は、人間の知識の本質的な限界と、人間の経験を超えたおそらく認識できない現実の性質を明らかにします。
ニーチェはこの考えを援用することで、人間の知覚の境界を無視する形而上学の主張を微妙に批判しています。それは、たとえ形而上学的世界が存在するとしても、そこへの私たちのアクセスは必然的に私たちの感覚的および認知的装置によって媒介されることを認識し、認識論にさらに深い謙虚さをもたらします。これは、見た目と現実、主観と客観の違いに関する現代の哲学的議論と強く共鳴し、意味と真実をどのように構築するかについての考察を引き起こし続けています。