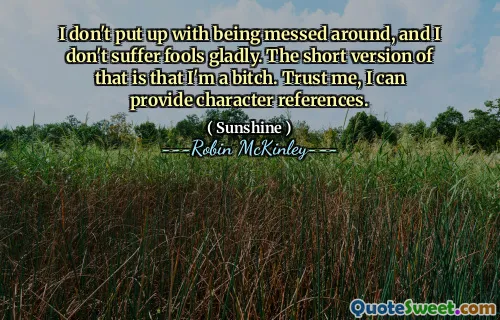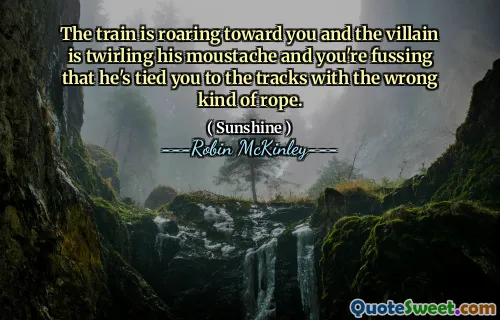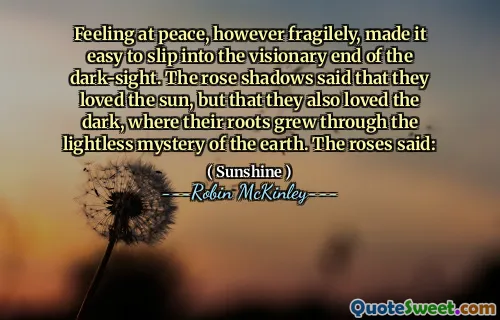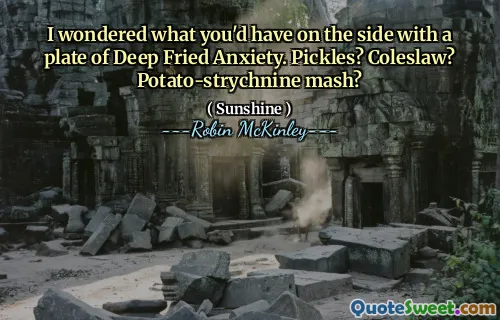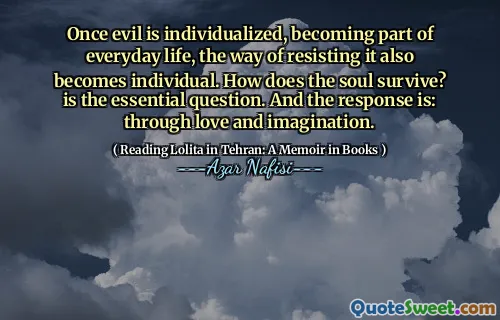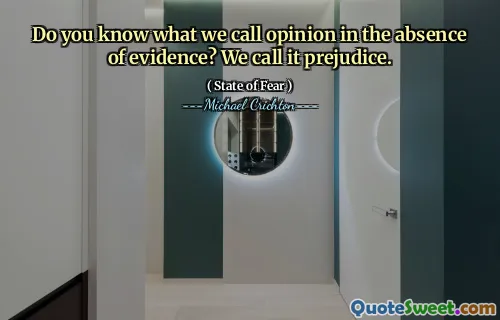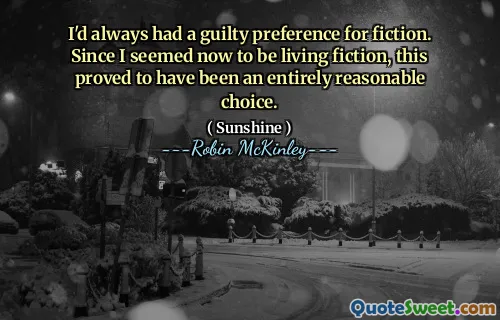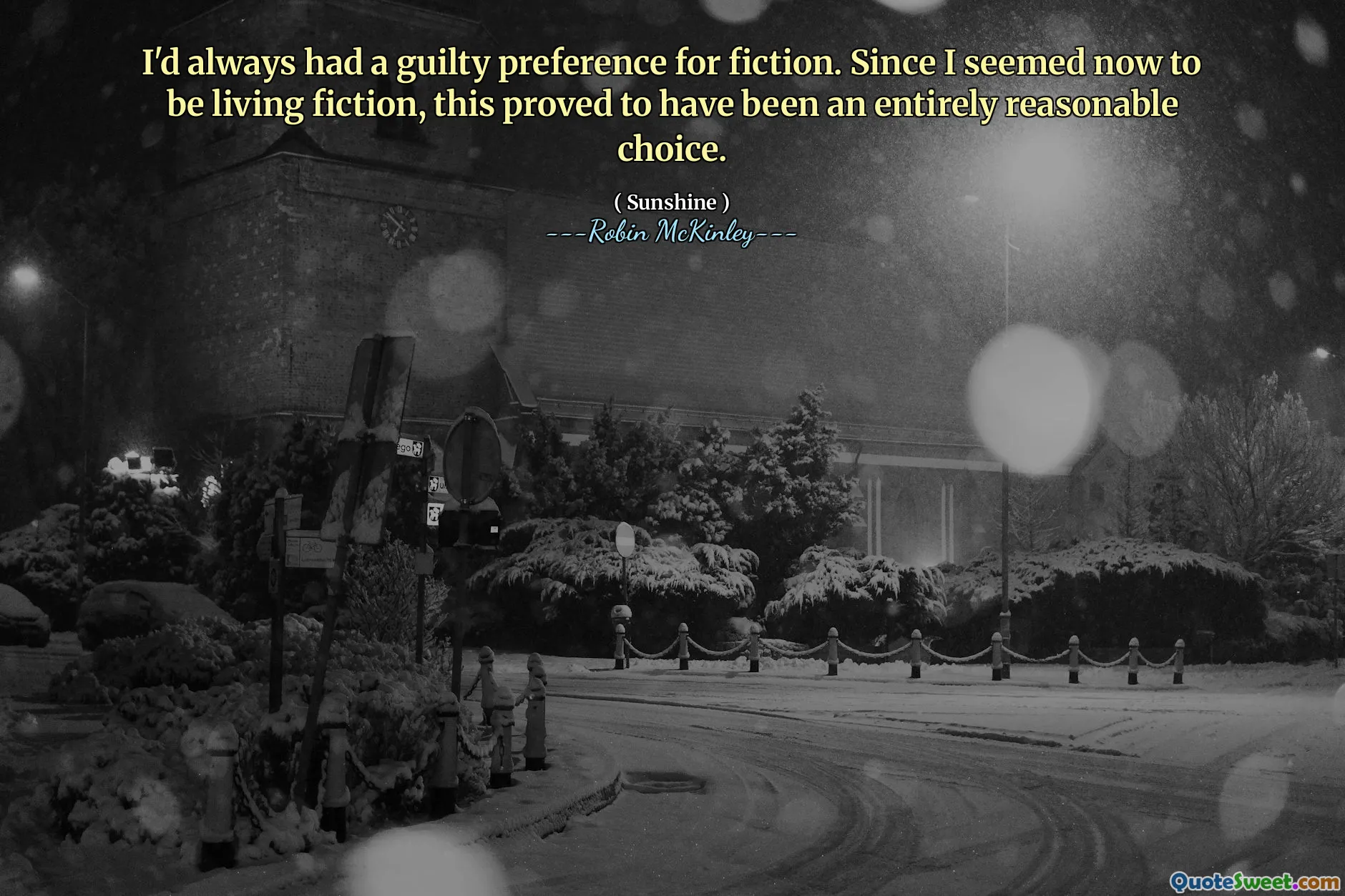
私はいつもフィクションに対して罪悪感を抱いていました。私は今、フィクションを生きているように思えたので、これはまったく合理的な選択であったことがわかりました。
(I'd always had a guilty preference for fiction. Since I seemed now to be living fiction, this proved to have been an entirely reasonable choice.)
(0
レビュー)
ロビン・マッキンリーの『サンシャイン』の中で、主人公はフィクションに対する自分の傾向を振り返り、現実よりもフィクションを好むことに常に罪悪感を感じていたと認めています。架空の物語に対する彼女の愛情は彼女の心の中に残り、人生を歩む中で葛藤の感覚を生み出しました。
しかし、彼女の人生が超現実的で架空の冒険へと展開するにつれて、彼女は自分の好みが正当であるだけでなく、自分の状況を考慮すると適切であることに気づきます。この認識は、フィクションが個人的な経験と深く共鳴し、現実と想像上のストーリーテリングの間の境界線を曖昧にする可能性があるという考えを強調します。
Rate the Quote
コメントとレビューを追加
ユーザーレビュー
0 件のレビューに基づいています
レビューはまだ追加されていません。
コメントがスパム,虐待的,トピック外,冒とく的,個人攻撃的,またはあらゆる種類の憎悪を助長する場合,コメントは投稿が承認されません。
もっと見る »
Today Birthdays
1955 -
Max Lucado
1946 -
John Piper
1842 -
William James
1907 -
Abraham Joshua Heschel
1887 -
Aldo Leopold
1755 -
Alexander Hamilton
1976 -
Alethea Kontis
1971 -
Mary J. Blige
1825 -
Bayard Taylor
1943 -
Jim Hightower
1885 -
Alice Paul
1923 -
Carroll Shelby
1928 -
David L. Wolper
1954 -
Kailash Satyarthi
1972 -
Amanda Peet
1946 -
Naomi Judd
1970 -
Malcolm D. Lee
1955 -
Christian Marclay
1973 -
Rahul Dravid
1987 -
Jamie Vardy
1942 -
Clarence Clemons
1992 -
Fatima Sana Shaikh
1948 -
Larry Harvey
1930 -
Rod Taylor
もっと見る »