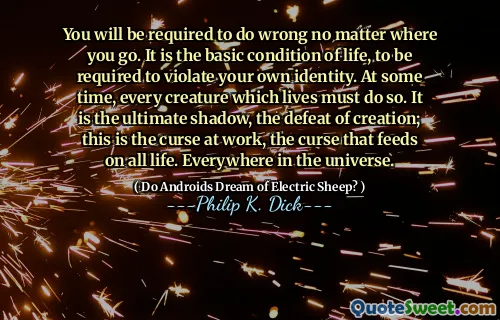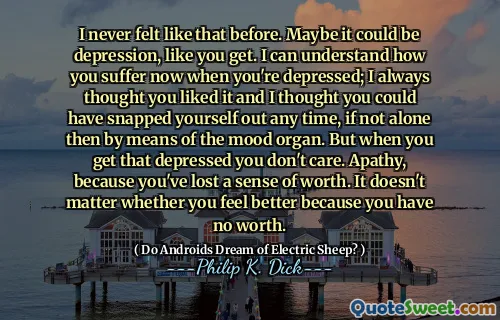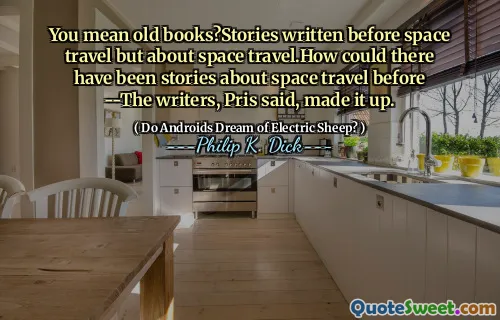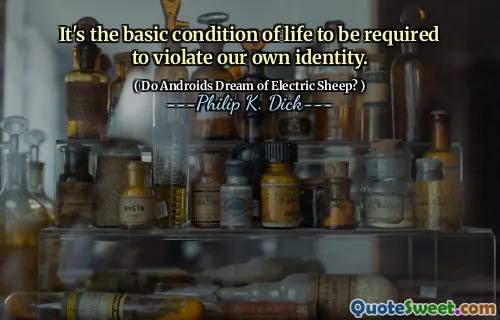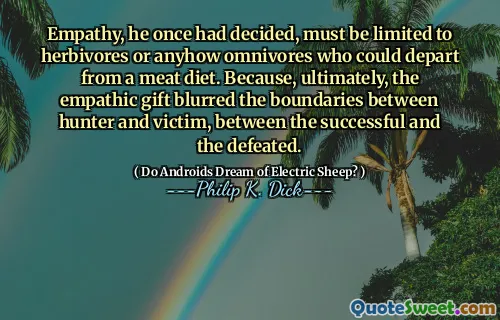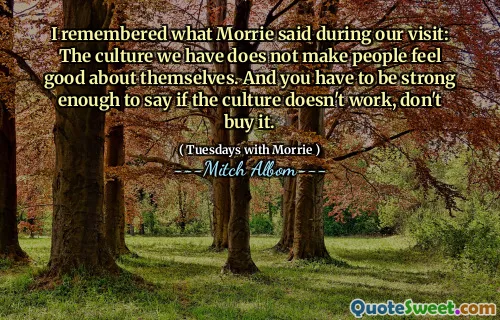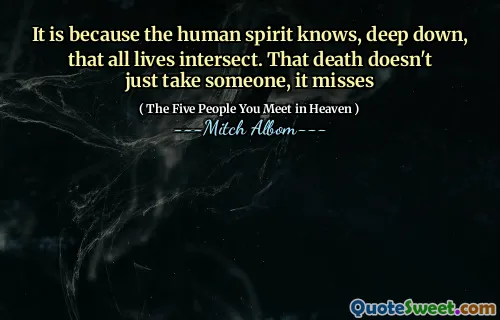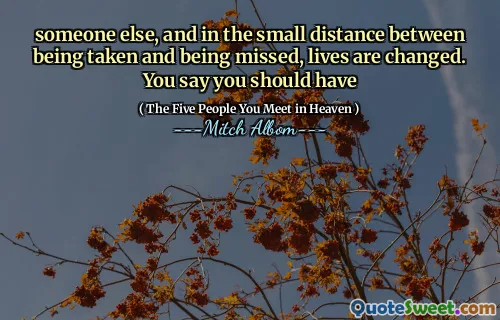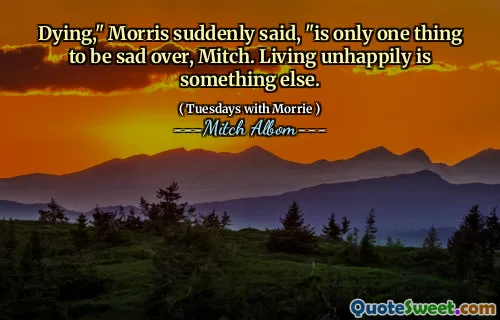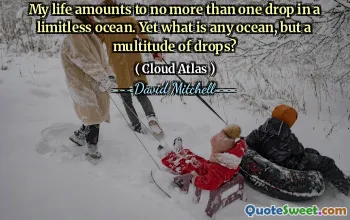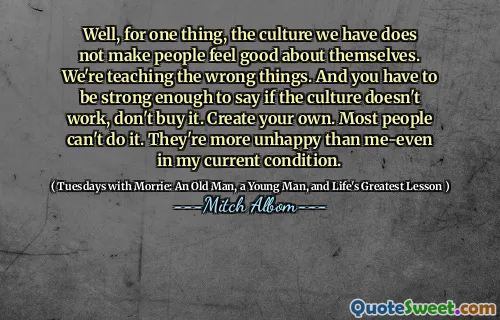しかし、暗い火は衰退しました。彼は他のアンドロイドと頻繁に目撃していたように、彼女から生命力がにじみ出ていました。古典的な辞任。それを生き、進化させるという20億年の圧力を伴う本物の生物が、それを和解させることはできなかった機械的で知的な受け入れ。
(Yet, the dark fire waned: the life force oozed out of her, as he had so often witnessed before with other androids. The classic resignation. Mechanical, intellectual acceptance of that which a genuine organism - with two billion years of the pressure to live and evolve hagriding it - could never have reconciled itself to.)
フィリップ・K・ディックの「ドー・アンドロイド・ドリーム・オブ・エレクトリック・シープ?」では、シーンは、アンドロイドが命の兆候を示し、人工生物と生きている生物の間の痛烈なコントラストを示している瞬間を捉えています。 「ダークファイア」の衰退への言及は、その運命の機械的な受け入れを反映して、Android内の生命の減少する火花を象徴しています。このシーンは、オブザーバーが同様のAndroidで抱えていた繰り返しの経験に共鳴し、有機生命体で見られる生存のための本能的な闘争と区別する特定の辞任を強調しています。
この辞任は、Androidと生き物の根本的な違いを強調しています。後者は生き残るための固有のドライブを持っていますが、数十億年以上の進化を形作りましたが、Androidのその終わりの受け入れは、真の感情的な深さの欠如を意味します。それは存在と意識の性質について深い疑問を提起し、それらの複雑なデザインにもかかわらず、アンドロイドはその本質を真に把握するのではなく、人間の経験をエミュレートできることを示唆しています。