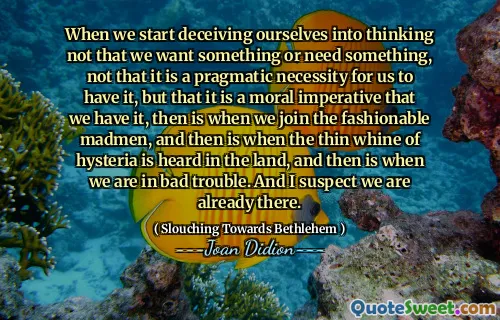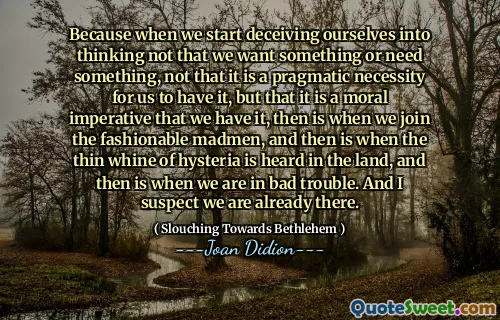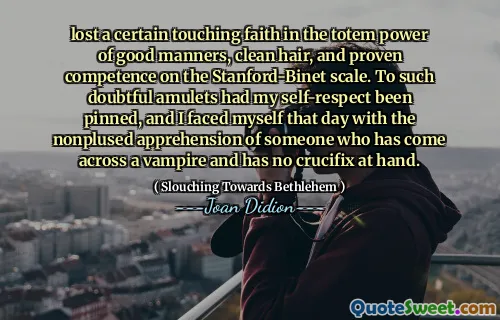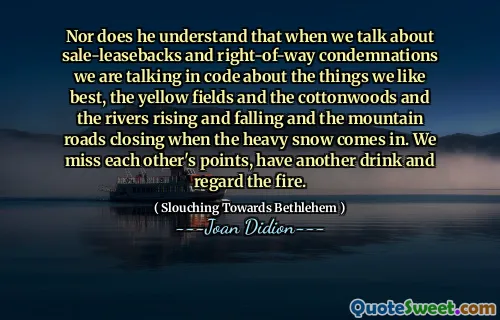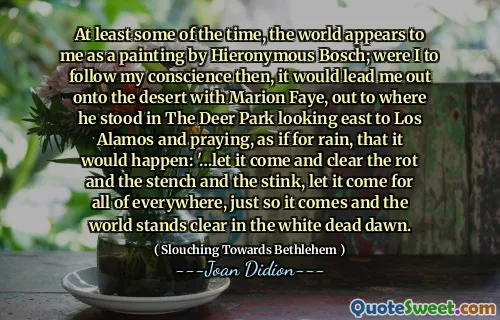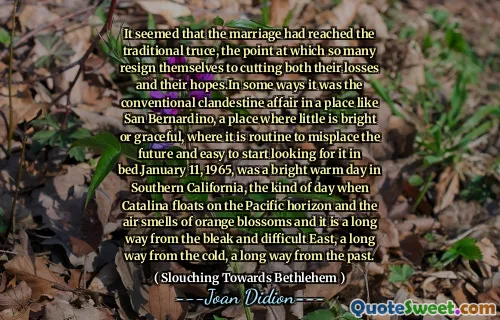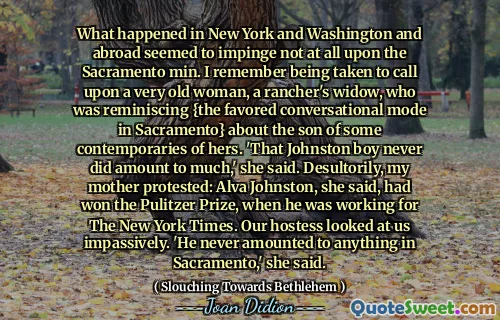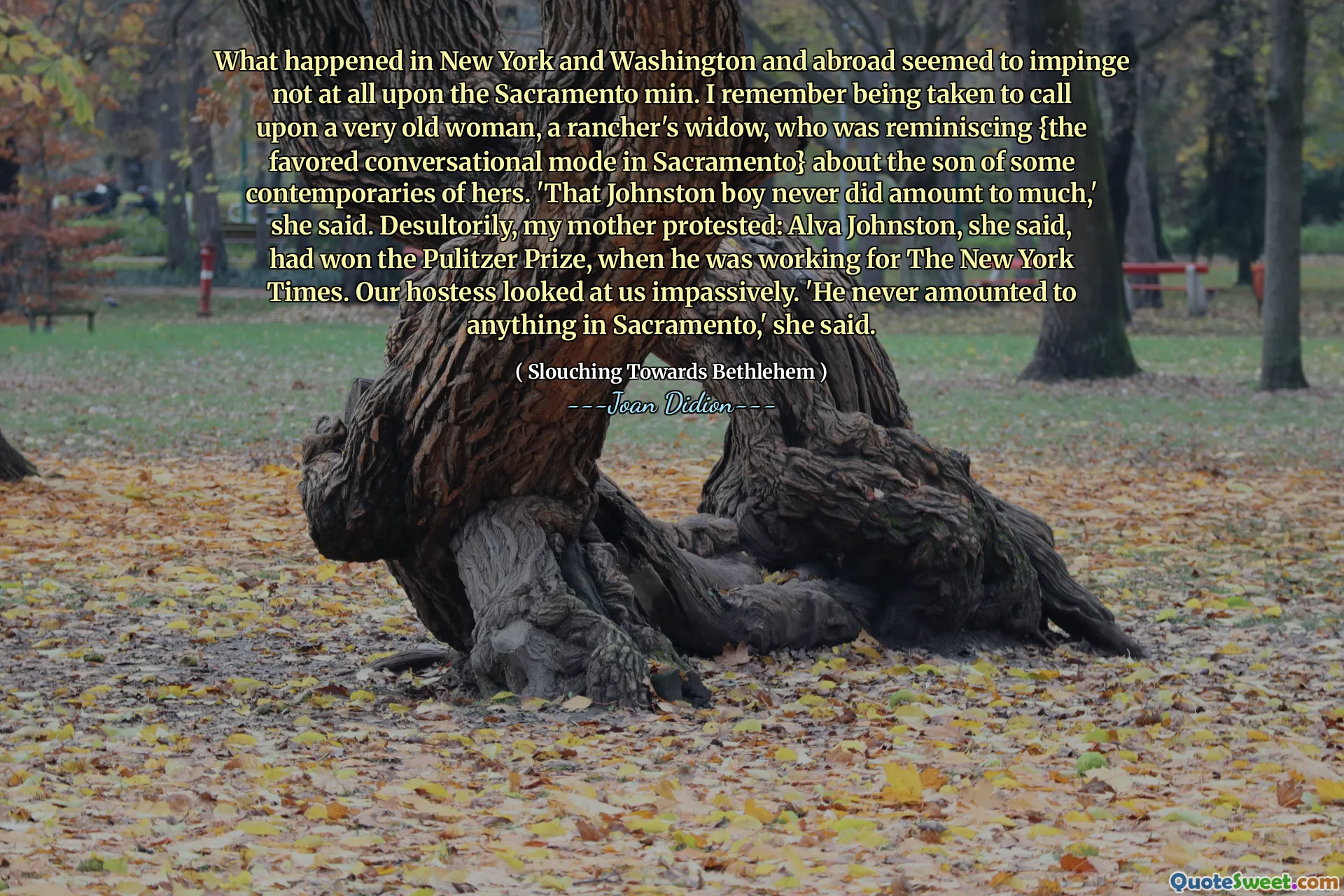
ニューヨークとワシントンと海外で何が起こったのかは、サクラメントミンにまったく妨げられていないようでした。彼女の同時代人の息子について{サクラメントで好まれた会話モード}を思い出していた牧場主の未亡人である非常に老婦人を呼びかけるようになったことを覚えています。 「ジョンストンの少年は決して多くをしたことがない」と彼女は言った。不誠実に、私の母は抗議しました:彼がニューヨークタイムズで働いていたとき、彼女は言った。私たちのホステスは私たちを冷静に見ました。 「彼はサクラメントでは決して何にもなりませんでした」と彼女は言いました。
(What happened in New York and Washington and abroad seemed to impinge not at all upon the Sacramento min. I remember being taken to call upon a very old woman, a rancher's widow, who was reminiscing {the favored conversational mode in Sacramento} about the son of some contemporaries of hers. 'That Johnston boy never did amount to much,' she said. Desultorily, my mother protested: Alva Johnston, she said, had won the Pulitzer Prize, when he was working for The New York Times. Our hostess looked at us impassively. 'He never amounted to anything in Sacramento,' she said.)
ジョアン・ディディオンの「ベツレヘムへの前かがみ」で、彼女は重要な国家出来事とサクラメントの地元の考え方との間の切断を振り返ります。逸話は、彼女の過去を思い出す高齢の牧場主の未亡人への訪問を共有し、他の場所で認識されている成果を減少させる地元の人物に焦点を当てていることを明らかにします。ニューヨークタイムズでのアルバ・ジョンストンのピューリッツァー賞を受賞したキャリアの彼女の解雇は、国民の成功よりもコミュニティを大切にするローカライズされた視点を例示しています。
ディディオンの経験は、サクラメント以外の業績が住民とは無関係であると思われる文化的格差を示しています。ジョンストンが「決して何にならない」という女性の主張は、地元の認識がより広範な成果を覆い隠し、孤立性のテーマを強調する方法を強調しています。そのような瞬間は、アイデンティティと認識の複雑さを明らかにし、より大きな成果に関係なく、自分の価値が彼らの直接の環境に深く結びついている可能性があることを示唆しています。