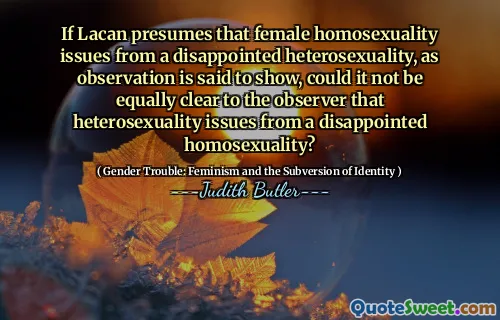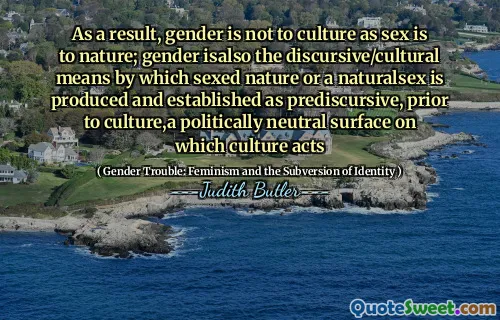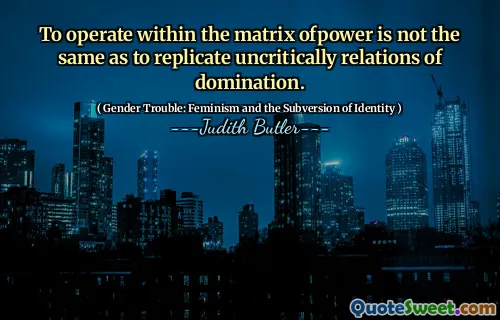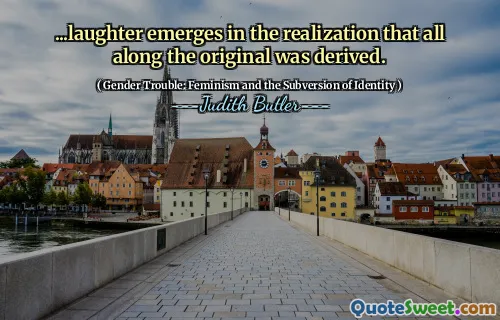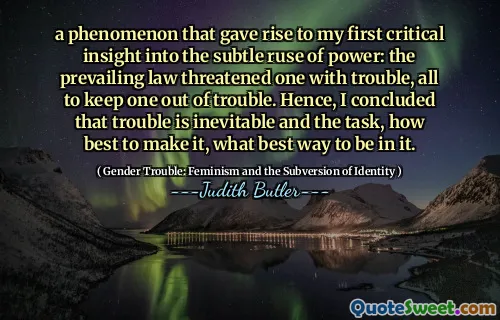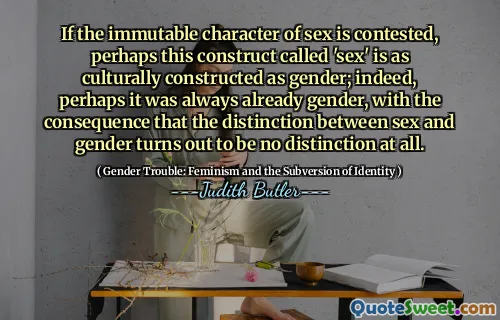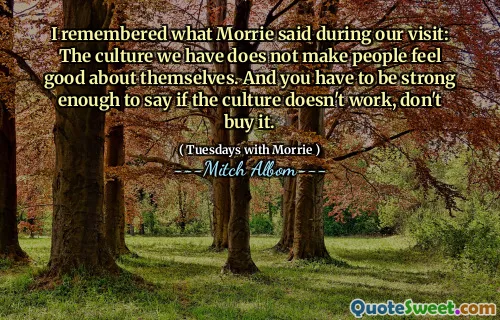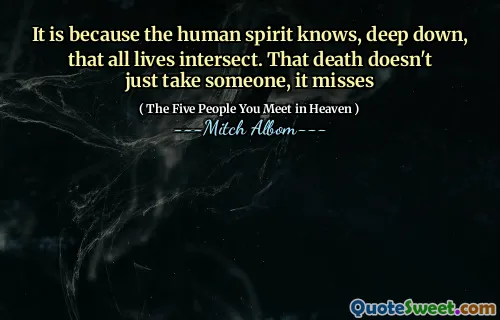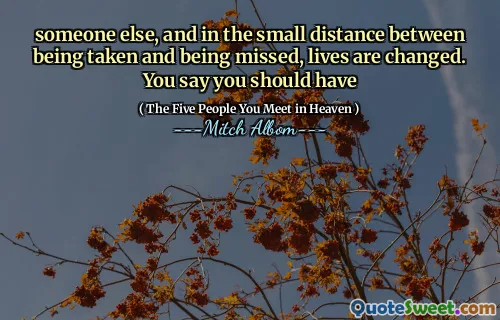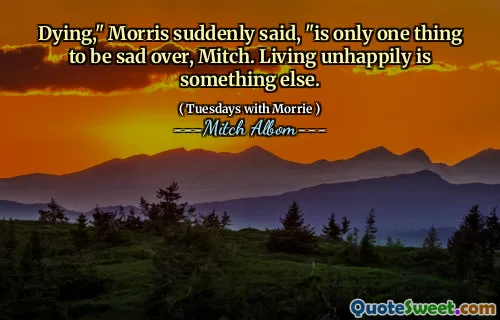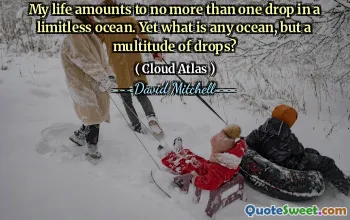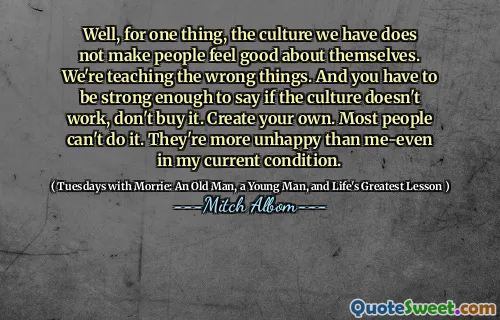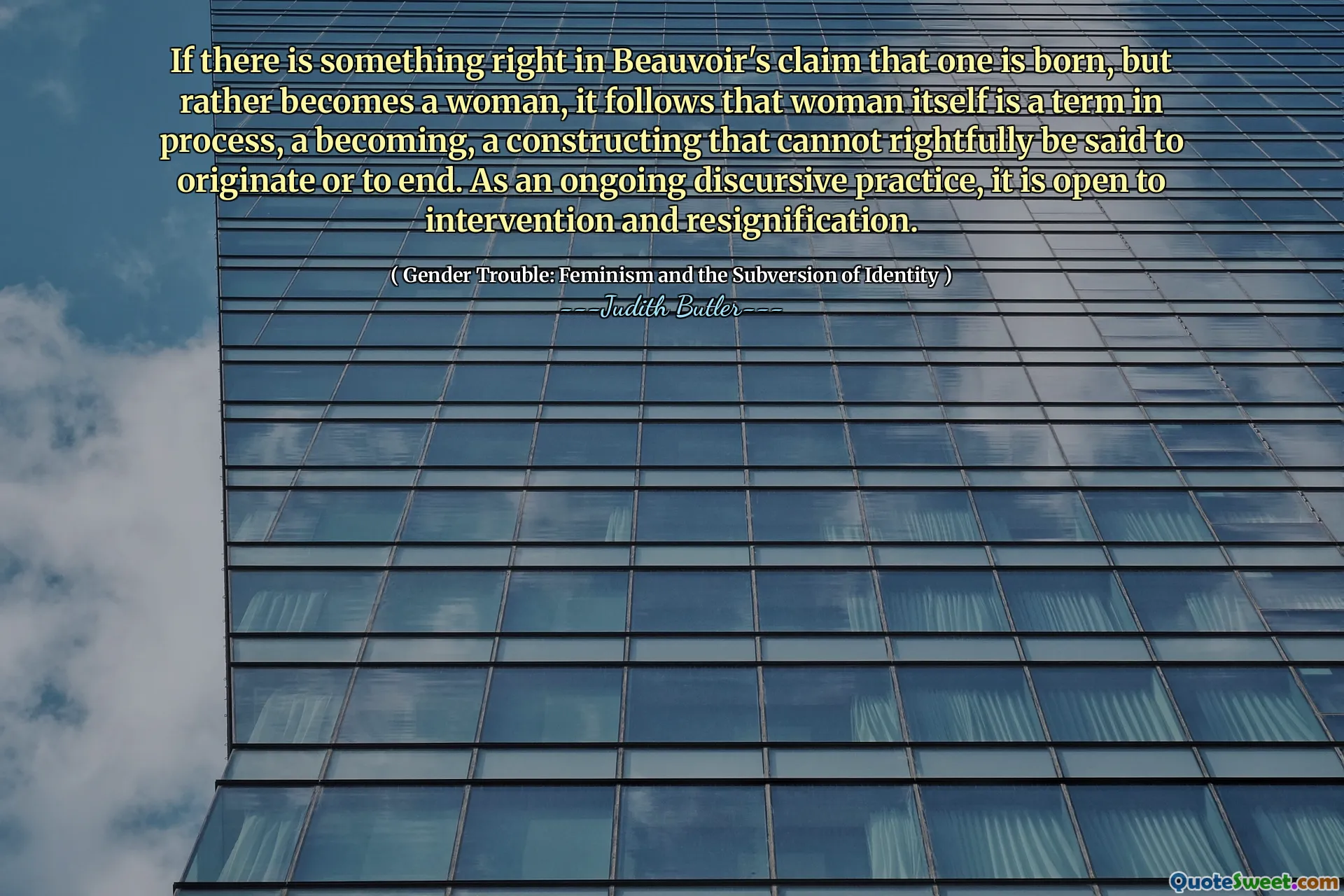
ボーヴォワールの主張に何かが生まれているが、むしろ女性になるという正しいことがある場合、それは女性自体がプロセスの用語であり、生まれていると言わない構築であるということです。継続的な議論の実践として、それは介入と辞任に対して開かれています。
(If there is something right in Beauvoir's claim that one is born, but rather becomes a woman, it follows that woman itself is a term in process, a becoming, a constructing that cannot rightfully be said to originate or to end. As an ongoing discursive practice, it is open to intervention and resignification.)
ジュディス・バトラーの「ジェンダートラブル」では、彼女はシモーヌ・デ・ボーヴォワールの主張を、本質的に女性ではなく、むしろ社会的および文化的プロセスを通じて1つになるという主張を振り返ります。この概念は、女性性のアイデンティティが固定されていないが、より広い議論の実践によって形作られた継続的に進化することを意味します。女性性は、簡単に定義したり閉じ込められたりすることができない動的な構造であることを示唆しています。
さらに、バトラーは、この継続的な進行中のプロセスが介入と再解釈の余地を可能にすることを強調しています。性同一性は事前に決定されていないため、挑戦して再定義される可能性があり、女性であることの意味は静的ではなく、社会的変化、個々の経験、政治運動に応じて変換できることを示しています。